奇蹟を信じますか?
一般的に言う奇跡と〈奇蹟〉では意味がちがいます。
奇跡とは理屈などでは説明ができない不思議な現象のことで、〈奇蹟〉とは神が意思を持ち起こしたとされる自然現象のこと。
そしてこの短編集に限ってはすべてが〈奇蹟〉のうえに成り立っています。
奇蹟を頼りに未来へ進もうとする主人公もいれば、奇蹟に人生を救われる主人公もいて、この短編集はまさに奇蹟の一冊と言えるでしょう。
恵まれた環境にいた者にもそうでなかった者にも、それは突然舞い降りるのでした。
著:浅田次郎
¥440 (2025/11/06 16:11時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
タップできるもくじ
『鉄道員』の概要

出典:Amazon公式サイト
| タイトル | 鉄道員 |
| 著者 | 浅田次郎 |
| 出版社 | 集英社 |
| 出版日 | 2000年3月17日 |
| ジャンル | やさしい奇蹟の短編集 |
8編からなる浅田次郎による短編集です。
奇蹟がテーマというだけあって心あたたまるものが多いです。
物語に入り込めたと思った途端に終わる、それが短編集というものでしょう。
しかしどのお話も、ここで終わってくれてよかったと思わされるものばかりでした。
『鉄道員』のあらすじ

冒頭で述べたように奇蹟とは、神がなんらかの意思を持って起こす自然現象のことです。
つまりそれは祝福ばかりではないのです。
もちろん祝福の場合もありますが、忠告であったり罰であったり……さまざまでしょう。
けれどこの短編集に集められたものはだいたいが祝福による奇蹟ですので、悲しい結末のものはありません。
たとえ主人公が登場人物が死のうと、そこにはたしかにぬくもりがあるのです。
8つのやさしい奇蹟
高倉健さんが主演で映画化もされていますので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
鉄道に命をかけたひとりの父親の生涯が、たくさんのぬくもりと共に終わっていくお話です。
そのように人の死に関するお話は『ラブ・レター』や『角筈にて』、『うらぼんえ』に『オリヲン座からの招待状』と、『鉄道員』含め合計5編あります。
会ったこともない妻からのラブレターを読んだことで自らの生き方を見直した男、理不尽に責められる孫娘のためにお盆に帰ってきた祖父、捨てた故郷で待っていてくれた小さな映画館の夫婦のお話でした。
『悪魔』と『伽羅』の2編は家庭教師としてやってきた男が悪魔だったというお話に、ブティックに営業周りをしている男たちが劇薬のような女店主と出会うことで呪われていくお話です。
残された『ろくでなしのサンタ』はというと、ようやく釈放された三太という男がほんものサンタになる、生きる力がみなぎる愛と祝福にまみれたお話です。
なつかしい哀しさに触れる
表題作の『鉄道員』や『角筈にて』『うらぼんえ』などは特にそうなのですが、どこかなつかしさを感じることができる作品です。
その掴みどころのないなつかしさは、夏の空に蝉の鳴き声、そのなかを祖父母や両親に手を引かれいっしょに歩いた記憶や景色……といえばわかりやすいのではないでしょうか。
そういった記憶がなくとも、日本人ならばその文章だけでなつかしく感じてしまうことはあると思うのです。
ふわふわとした頼りないそんななつかしさに心揺さぶられたいとき、浅田次郎のこの短編集はもってこいと言えるでしょう。
角筈にて
4編目の『角筈にて』は、父親に捨てられた子どもの心理描写が残酷なほどやさしく、そして哀しみにあふれています。
貫井恭一という男性が仕事の事情で日本を離れなければならないころに、幼い自分を捨てて女のところへ行ってしまった父親を見つけるお話です。
とっくに死んでしまっていた父親との再会で、貫井は幼い子どもに戻りあのころのように父親に縋るのでした。
「恭ちゃん。すまないけど、おとうさんはお前を捨てる」
それは父親が自分を捨てたあのころからずっと、貫井が聞きたかった言葉でした。
「ありがとう、おとうさん。ありがとうございました」
そして貫井が父親にかけたその心からの言葉で、父親はきっと浮かばれたことでしょう。
『鉄道員』の次に奇蹟というテーマに相応しい作品だと思います。
『鉄道員』を読んだ感想

奇蹟はだれにでも起こりうる、特別な事象なのだと再認識できました。
忠告や罰が含まれていようと、それでも私はそれらを祝福と呼びたいです。
なぜならきっと、祝福とはそういうものであると思うからです。
明日への希望
明日も生きていける、そう思える作品というものは案外世の中にたくさんあります。
それは絵であったり音楽であったり、はたまた幸運な出来事であったり……。
浅田次郎によるこの短編集もきっとそうでしょう。
生きる糧といえば少し大げさかもしれませんが、文学作品にもそんな力があるのだと強く思いました。
なにかと肩身が狭い文学というジャンルですが、それを理解したうえでみんなに読んで欲しいと思える、素敵な作品です。
胸を締めつける描写
なつかしさとはもともと胸を締めつけるものですが、もちろんその表現は人によって異なります。
浅田次郎という作家の、特になつかしさという点においての表現力は凄まじいものがあると、私は感じました。
心を抉ることなくただただ純粋に締めつける、その力は『角筈にて』の引用した台詞でよくわかってもらえたかと思います。
漢字と平仮名の使い方、句読点の使い方など、登場人物の息遣いまでが聞こえてくるほどです。
ときに実写よりも訴える力を持つ文学というジャンルで、浅田次郎という作家はやはり飛び抜けてすごい、そう言わざるをえません。
浅田次郎の想い
浅田次郎はあとがきにて、自分は科学的な説明がつかないことは信じていないたちであると述べています。
それでもこの〈奇蹟〉をテーマにした8つの物語を再読して、
「読者の心に小さな奇蹟が起こってくれるなら幸いである、と思った。」
とも言っているのです。
そしてこの短編集はどうしても小説家になりたかった自分にも奇蹟をもたらしたということでした。
つまりこの浅田次郎著の『鉄道員』という短編集は、紛れもなく浅田次郎の手によって生まれた〈奇蹟〉なのです。
そればっかりは否定のしようがありません。
奇蹟を書いた作家が、自分も奇蹟に祝福されたというのですから。
『鉄道員』はどんな人におすすめ?

心あたたまる短編集ということで、どこか心が傷ついてしまった人などにおすすめしたい気持ちはもちろんあるのですが、それでもやはり、死に触れる作品も多いのでその限りではありません。
親しい人を亡くしていたりする人にも、ぜひ読んで欲しいと思います。
たとえば他にも、
- 心の穴があいたように哀しい人
- あたたかい短編集が読みたい人
- 静かに泣ける作品が読みたい人
などにおすすめしたいですし、単純にさっと読める本を探している人にもよいでしょう。
おわりに|自身や大切な存在への祝福、人はそれを奇蹟と呼びます

私にはまだ、親族や親しい人を亡くした記憶がありません。
いずれ必ずそういう日がくるのでしょうが、その日までにこの短編集に出会えたことに感謝しています。
まるでいつか来るその日のための心の準備ができたというか、そんな気がしてならないのです。
死というものの価値観が変わったわけではありませんし、この短編集にもそのような力があると言いたいわけではありません。
ただ、人と人との繋がりというものは美しいのだと、教えてもらった気がします。
著:浅田次郎
¥440 (2025/11/06 16:11時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
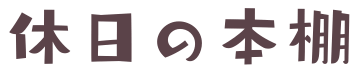
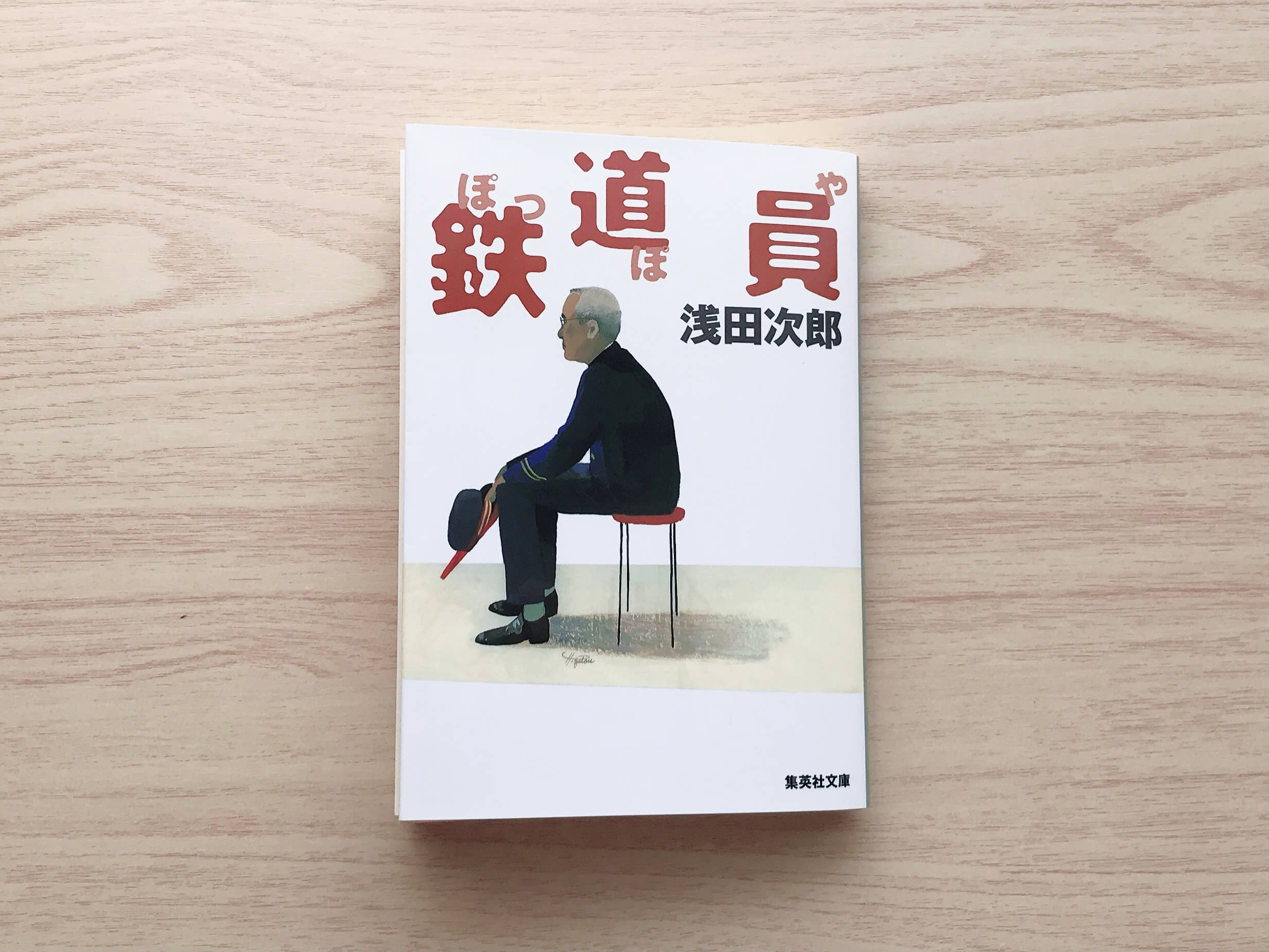

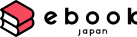





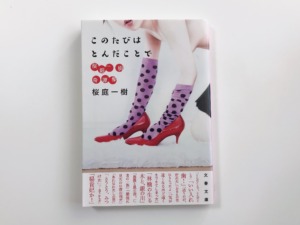
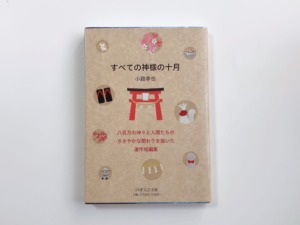
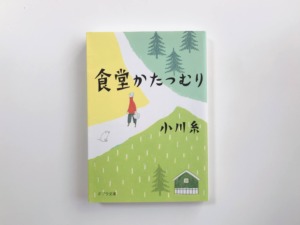
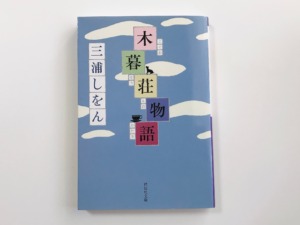
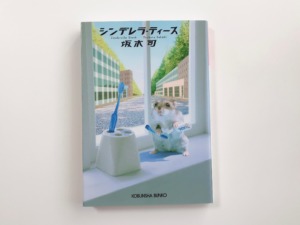
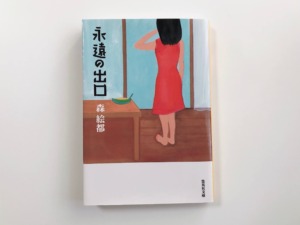
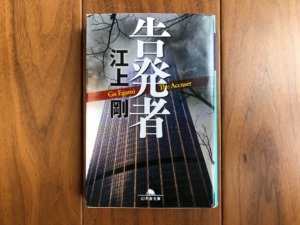
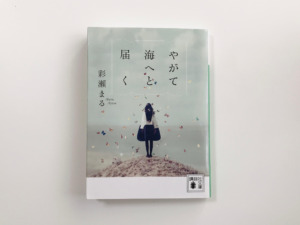
コメント